月間アーカイブ
- 2026年02月
- 2026年01月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年09月
- 2025年08月
- 2025年07月
- 2025年06月
- 2025年05月
- 2025年04月
- 2025年03月
- 2025年02月
- 2025年01月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年09月
- 2024年08月
- 2024年07月
- 2024年06月
- 2024年05月
- 2024年04月
- 2024年03月
- 2024年02月
- 2024年01月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年09月
- 2023年08月
- 2023年07月
- 2023年06月
- 2023年05月
- 2023年04月
- 2023年03月
- 2023年02月
- 2023年01月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年09月
- 2022年08月
- 2022年07月
- 2022年06月
- 2022年05月
- 2022年04月
- 2022年03月
- 2022年02月
- 2022年01月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年09月
- 2021年08月
- 2021年07月
- 2021年06月
ブログ
2025年11月18日
どんまいサロンの秋のイベントに参加してきました!
先日、当法人のサロン【さろんだぞう】にて
秋のイベントがあり
ゆっくりクラブの利用者さん、参加してきました!



サロン担当の職員が、業務の合間を縫って
アイデアを出し合い、ささやかですが
利用者さんに楽しんでいただけるよう、企画しました♪
仮装して登場される利用者さんもおられ、楽しい時間となりました☆
また、一緒に楽しみましょうね☺
2025年11月18日
こんにちは、どんまいクラブのKです。
こんにちは、どんまいクラブのKです。
今回、初めてどんまいクラブのブログを書きます。
とりあえず今回は、自分の趣味である旅客機の写真撮影を題材にしてみます。
エバー航空À321-211ハローキティのPinkyJet
この特別塗装の機体は、左右の絵柄が違うので見ても撮っても楽しめる機体です。


大阪・関西万博の特別デザイン機「EXPO2025 ANA JET」
ANAウイングスB737-881
機体のデザインは、大阪・関西万博のイメージしたカラーとANAコーポレートカラーを流線型に融合させ、風に乗って未来へ向けて飛び立つことを想起させる特別デザインになっているみたいです。


2025年11月04日
べらぼう
こんにちは。
いんさつの咲々屋マスコットキャラクターの咲子です。

今月は12月21日(日)まで開催されている「蔦重と歌麿・写楽」展全3章を紹介します。
これはNHK大河ドラマ「べらぼう」の放送開始を機に、歌麿館で喜多川歌麿をはじめとする当時の浮世絵師たちの作品を展示しているものです。
展示場所は、県立自然公園の鹿野川湖畔を望む丘の上に、大洲市立肱川風の博物館があり、隣接する歌麿館で、浮世絵の発達段階や歴史をパネルで紹介しています。日本を代表する浮世絵師 喜多川歌麿の版本は世界中に4枚存在しており、そのうち2枚を展示しています。
2025年大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺」は、江戸時代を舞台に、数多の浮世絵師・作家の才能を見出して、世に送り出した出版人「蔦屋重三郎」(つたやじゅうざぶろう)の波乱万丈の人生を描いた物語です。
また「歌麿café」では和テイストの空間の中で至福の一杯がいただけます。

《蔦屋重三郎とは》
重三郎は、江戸中期から後期にかけて活動した版元です。
生まれも育ちも吉原だった重三郎の細見(風俗情報誌)は充実しており、お店の「蔦屋」の地位を確固たるものにしました。重三郎は吉原内部の動向を知っており、出版業界との橋渡しをしました。
黄表紙(注1)、洒落本(注2)、狂歌本(注3)の作品を刊行し、一線級の版元として認知されるようになり、日本橋進出に成功しました。その後狂歌師としての活動も開始し、著名な狂歌師とのつながりを持ちました。そして、喜多川歌麿(美人画)や東洲斎写楽(役者絵)と大きな仕事をしました。
晩年は出版界の冬の時代を乗り越えようと努力しましたが、病に倒れ47歳で没しました。死因は脚気と伝えられています。
(注1)黄表紙・・・知的でナンセンスな笑いと当時の現実世界を踏まえた写実性が特徴の大人向け読み物。
(注2)洒落本・・・吉原などの遊里での習慣や風俗、客と遊女のやり取りなどの会話の書かれた読み物。小説に近い。
(注3)狂歌本・・・社会風刺や皮肉を盛り込んだ短歌のようなもの。


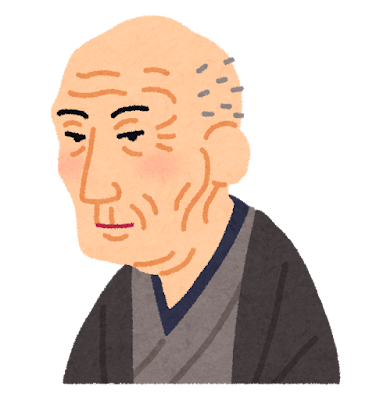
《TSUTAYAと蔦重の関係は?》
なお、現在ある「TSUTAYA」(蔦屋書店)は、蔦屋重三郎の子孫ではなく、創業者である「増田宗昭」(ますだむねあき)さんの祖父が営んでいた置屋の屋号が「蔦屋」だったことから付けられたとのこと。 しかし、全く関係ない訳ではなく、その祖父の屋号は、蔦屋重三郎にあやかって名付けられたと伝えられています。
今、葛飾北斎の娘(主演 長澤まさみ)を題材にした映画が上映されています。これを機会に見に行きたいと思います。浮世絵ブームが来るかもしれませんね。
